
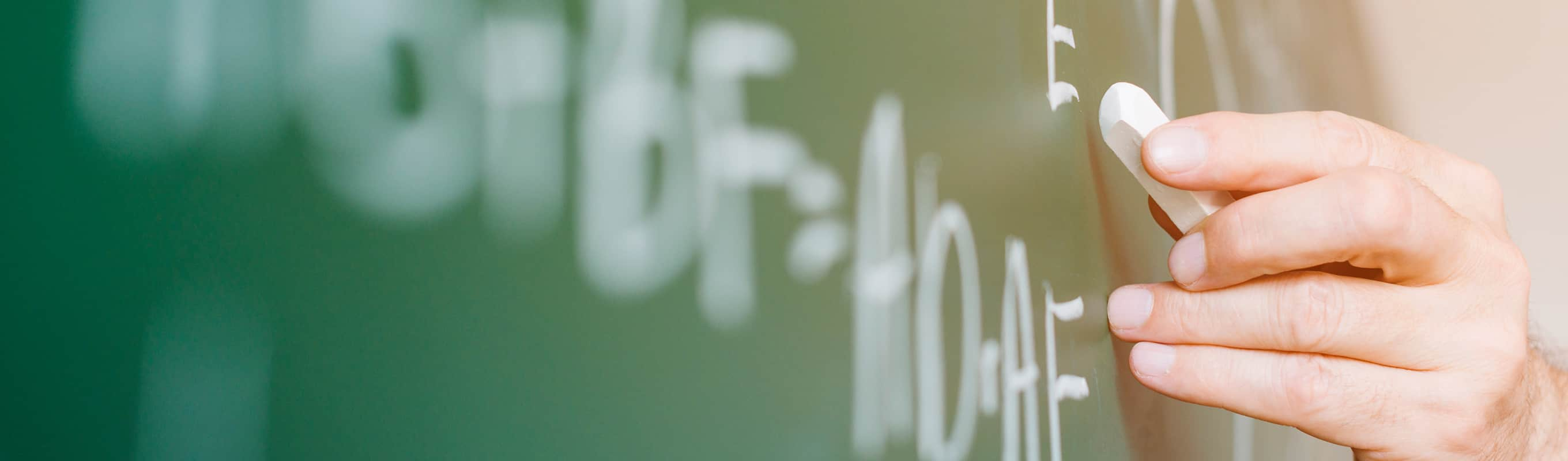









土地家屋調査士は、昭和25年7月31日に法律第228号で公布された「土地家屋調査士法」により創設された国家資格です。
不動産の登記制度において土地や建物を詳細に調査することで各種の権利の目的物を明確にする役目を担っています。
「不動産登記」の目的は、国家が不動産取引の完全を保証し、誰もが安心して取引できるようにすることです。
主に不動産の物理的現況(どこに、どれくらいの広さの建物、土地なのか等)を登記簿に記録するために創設された国家資格です。
不動産の登記制度において土地や建物を詳細に調査すること表題部に登記すること、これを表示登記といいますが、この表示登記の申請書の作成及び申請代理を業務とするものです。この業務に関して報酬を得ることのできるのは、土地家屋調査士として登録されているものに限ります。
また、土地の境界に関する調査・測量のプロフェッショナルとして、国民の財産として大切な不動産「土地」・「建物」に関して
大変に重要なサポート約として活躍しています。


| 試験概要 |
法務省が実施する土地家屋調査士試験に合格することです。 |
|---|---|
| 受験資格 |
制限なし、誰でも受験できます。筆記試験(午前試験と午後試験)と口述試験からなる。ただし、午前試験は測量士・測量士補、一級建築士・二級建築士の有資格者は免除されます。 |
| 試験内容 |
不動産の表示に関する登記につき必要と認められる事項であって、次に掲げるもの
|
| 試験科目 |
※免除資格(建築士・測量士・測量士補等)のない方
|
| 備考 |
※詳細は、法務省「土地家屋調査士資格試験ページ」にてご確認下さい。 |
測量法及び測量法施行令に基づいて行われる国家試験です。また、測量士補となるのに必要な専門的技術を有するかどうかを判定するために行い、試験に合格すれば、測量士補となる資格を取得できます。試験は年1回実施され、どなたでも受験が可能です。
なお、測量士補は、測量士の作成した基本測量。公共測量等の計画に従い、実地に測量の作業を行う事を仕事としています。
※「測量士補」の資格取得で土地家屋調査士の午前試験が免除されます。
| 受験資格 |
特に制限なく、誰でも受けられます。 |
|---|---|
| 試験形式 |
五肢択一式 計28問 |
| 試験実施日 |
例年5月第3日曜日 |
| 所要時間 |
3時間 |
| 試験科目 |
|
| 備考 |
※測量士補試験は電卓使用不可 |
| 合否について |
6月の第4木曜日に発表
国土地理院、国土地理院各地方測量部及び国土地理院沖縄支所において合格者の受験番号及び氏名を公告するほか、全受験者宛てに試験の結果(合否)が通知され、不合格となった方には試験結果に添えて成績が通知されます。 |