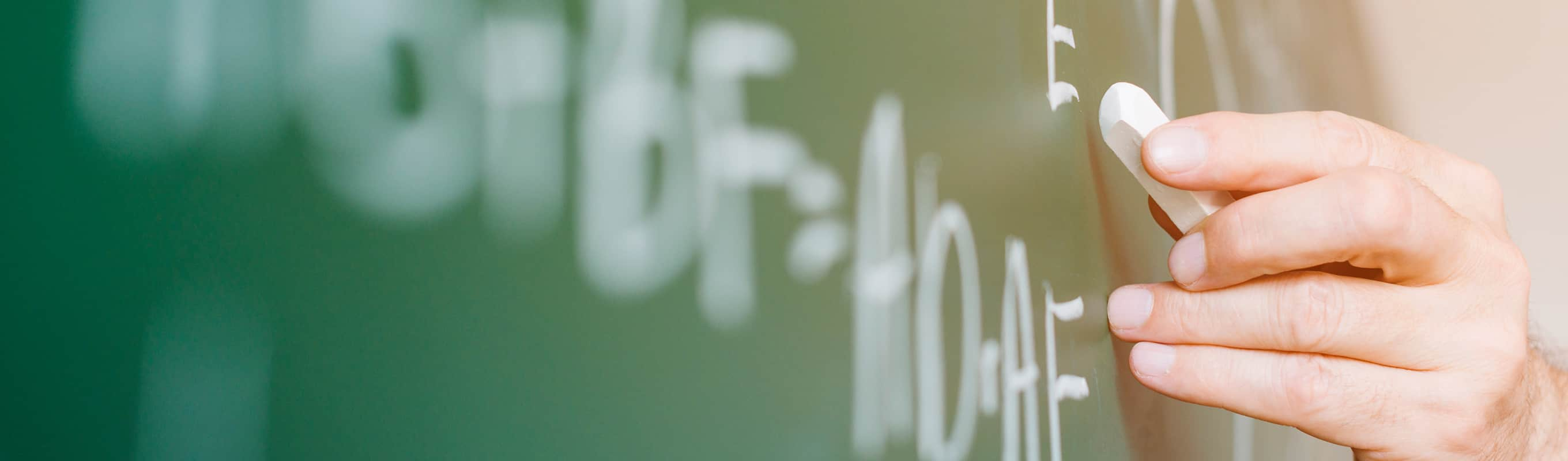測量事務所(土地家屋調査士事務所併設)に勤務しておりましたが、昨今の不況による社会的状況、また、この業界に身をおいてきて、今後一歩上のランクに自分自身を高めていくために、土地家屋調査士の資格を取得しようと決意し、勉強を開始しました。
仕事上、実務は経験していたので何とか独学でと思い、1年目は過去問の問題集と参考書を購入し、独学で受験に臨みましたが択一問題の段階で足切りにあうほどのさんざんの結果でした。これでは、とても合格に近づけないと考え、通信教育で基礎から勉強に取り組むことにしました。いくつかの通信教育制度の中から早稲田法科の「調査士総合Aコース」を受講することに決めました。早稲田法科を選んだ理由は、①合格者の実績があったこと②教育訓練給付制度が利用できたこと③他校と比べて値段が安かったことです。家族があり仕事をやめて勉強に専念することができない状況であったため、経済的な観点、時間的な観点が重要な選択理由でした。ただ、たしかパンフレットに書かれてあった「深田マジック」という言葉に強く心を動かされたのも事実です。
通信教育を始めてからの勉強法は、送られてきたテキストや課題をこなすほか、DVDの音声をICレコーダーに録音し、それを常に携帯して車での移動時間や少しの空き時間があれば、とにかく聴くようにしました。GW集中講座にも参加し、講義に臨むまでは大変緊張していましたが、家族的な雰囲気で質問もしやすかったので、松元先生の生の講義を聴いて断片的であった知識がかなり整理して頭に入りました。2回目の試験の直前(お盆の頃)には、過去問も時間内に解答することができ、なんとか合格できるのではないかとの手ごたえをもって試験に臨みました。
しかし、2回目の受験は合格点に3点足りずに不合格でした。最大のミスは、土地の書式問題で冷静さを欠き、計算ミスをしてしまったことです。また、択一であと2問正解できていればとの悔しさもありました。もう一度、自分の弱点を見つめなおし、3回目は出来が悪くても合格のレベルに達するレベルまで実力を高めることを目標に勉強を再開しました。
まず、択一問題は5択の選択肢を消去法で選択肢を減らして、おそらくこれが正解だろうというようなことをなくすために、平成9年以降の過去問をすべてコピーし、2~3の選択肢ごとに表面に問題を裏面に解答を貼り付け、出題年度、問題番号、出題テーマを書き、チェック欄をもうけてB6サイズのコンパクトなオリジナルの問題集を作成し、移動時間や少しの空時間を利用して繰り返し解答の練習をしました。作成には、かなり時間を費やしましたが、移動時間に漫然と参考書を読んだり、ICレコーダーに録音した講義を聴くよりも、自分が理解できていない部分が明確になり、大変役に立ちました。特に平日はまとまった勉強時間がとれない自分にとっては、机にむかっている以外の時間、いわゆる「細切れの時間」がとても重要となります。一日わずか20分であっても、2ヶ月続ければ20時間にもなります。また机に向かっている時とは環境が異なるので、記憶する時の集中力もむしろ高まったのではないかと思います。
書式問題については、机にむかった時には、とにかく書式問題に多く取り組み図面を早く正確に仕上げる、また計算ミスをなくす訓練に心がけました。それと同時に1秒でも時間短縮するために、道具にもこだわりました。たとえば、市販の三角スケールを使用した場合、試験ではほとんど1/250と1/500のスケールしか使わないので、そのスケールを探すだけでも時間を短縮できるように1/250と1/500だけのスケールがないかを探しました。(最終的に使用したのが、バンコ株式会社の特殊両面スケールシリーズの1/250と1/500の部分を切り取って使用しました。しかし、材質がやわらかく、線を引くのには不向きな面もありました。スケールつきの三角定規も市販されていますが、1/250と1/500のみの定規があればと思いました。)使用するペンもさまざまな種類のペンを購入して書く易く、図面の見栄えがいいものを研究しました。(最終的に使用したのは、三菱のuni-ballのSigno超極細でインクの出がよく、細い線が描けるので使用しましたが、試験本番の解答用紙では、少しにじみがでたので、パイロットのSUPER-GP0.5のボールペンの方がよかったかなと思います。)また、問題検討に使用するマーカーもキャップ式のものではなく、ノック式のものを探して使用しました。
3回目の受験に際しては、全国答案練習コースを受講し、GWやお盆の連休には図書館や有料の自習室を借りて、1日10時間、過去問と答練の問題を実践的に取り組みました。
いよいよ試験の当日、かなり自信をもって臨んだのですが、試験会場が前年とは変わり、クーラーがなく、また机が小さくて試験としては充分な環境とは言えず、また土地の書式問題では、いままでの過去問にはない論点の問題が出て、座標計算、面積計算が一部できませんでした。(たしか、答練の松元先生の問題で同じ論点の問題がでていたのに、その時はこんな問題は出ないだろうと思ってしまい、悔やんでいます)答練の講義の中でたとえ座標計算ができなくても、できるところは図面も含めて、あきらめずに解答することと、いわれていたことを思い出して出来るところを全て書きましたが、自分自身の手ごたえとしては、これで合格という自信が持てる解答ではありませんでした。
自己採点では、合格でも不合格でもギリギリのラインだろうと思っていましたが、結果は合格。インターネットで自分の受験番号を見つけたときの喜びと感動は、忘れられません。
口述試験にあたり、東京まで出向いて深田先生、松元先生の模擬試験も受けさせていただき、口述試験は落ち着いて解答することができ、最終合格を勝ち取ることができました。
今回の試験で最後に合否をわけたのは答練の講義で、たとえ座標計算ができなくても、出来るところを全て解答し、図面を仕上げること。とのアドバイスだったと実感します。受験勉強を通して感じることは、家庭をもち、仕事をしながら勉強する場合は、時間との戦いであるということです。仕事も忙しく、家に帰れば子供もいる、家のローンを抱え、地域の活動も無視することが出来ない環境の中、勉強時間は多いにこしたことはないのは言うまでもありませんが、時間を作る工夫、集中する環境を作る工夫と知恵が必要です。私の場合は、「細切れの時間」と休日にどれだけ効率的に勉強できるかが本当に勝負でした。また、「1年で必ず合格する」と決意することだと思います。実際は3年かかりましたが、モチベーションを保つためには将来のビジョンを持つことと同時に「必ず合格する」という深い決意が必要だと感じます。そして、受験勉強の期間と家族の理解、そして協力に対しては感謝の念でいっぱいです。
最後に深田先生、松元先生はじめ、講師の先生方に感謝するとともに、スタッフの方々にもいろいろな問い合わせや要求に対して決して事務的な対応ではなく、親身になって配慮していただき、感謝しております。本当にありがとうございました。