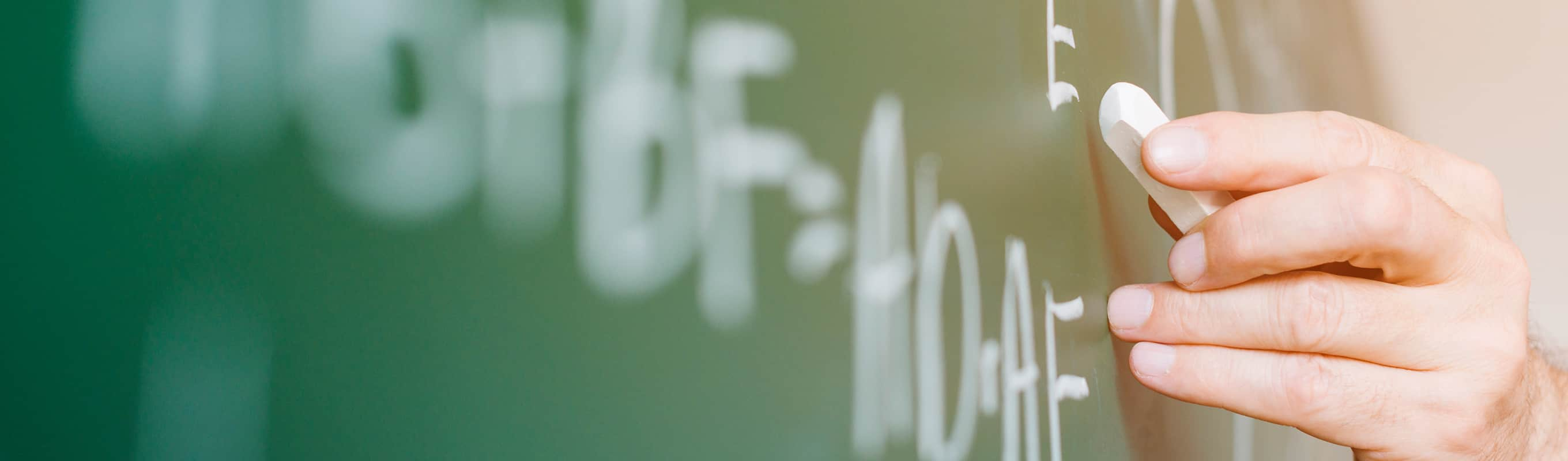はじめに
私は、土地家屋調査士試験に3回目で合格することができました。今までの受験生活においては、失敗や結果の出ない日々の繰り返しでありました。勉強を進めていく中で、過去の合格体験記から参考にしたことも数多くあり、私自身の体験がこれから調査士試験に臨まれる方々に少しでもお役に立てれば幸いです。
調査士受験のきっかけ
もともと測量会社で働いていたこともあり、測量のことはある程度理解はできていました。その当時から土地家屋調査士という資格のことも知っていましたが難しい試験であるという勝手な思い込みをしていました。ある日、知人から境界のことで相談を受けたのですが、内容が全然わからず何も答えることができませんでした。このような出来事があったため、人の役に立つことがしたい、この問題を解決していきたいと思い土地家屋調査士を目指すことにしました。ただ、今までの測量の経験が調査士試験では足かせとなってしまったことがこの時点では想像もしていませんでしたが・・・。
早稲田法科を選択した理由
本格的に受験勉強を始めたのが1月からで、このときは他校の基礎講座を受講していました。ネットから配信される映像とテキストで勉強を行い、択一も書式もよく理解できないまま1回目の本試験を受けましたが択一9問しか正解できず足切りにあいました。このままでは到底受かることができないと考え、以前から所持していた土地家屋調査士受験100講[Ⅰ]理論編の内容を理解したいと思い、本試験会場で配布されていた通信教育講座の中から、「本試験パーフェクト合格講座」をホームページで確認し、受講することに決めました。この講座を受講した理由は、受験100講を中心とした内容であり、答案練習を含め本試験のポイントを網羅している点が大きな理由でした。このとき、改めて予備校選びの重要性を痛感したとともに、せっかく所持していた100講をほとんど読まず放置していたことを大いに反省して、新たな気持ちで受験勉強を行うことにしました。
2回目の挑戦
教材が届くまでの間、受験100講を一通り読み込みましたが、読めない漢字が多く意味のわからないまま進めていました。この年から100講が改訂4版に変わったため、今まで所持していた3版はほとんど使うことがなくなり少し残念な気分になりましたが、新しくなった教科書で学習ができるということもあり繰り返し読み込みを行っていました。ようやく教材が届き、DVDで講義内容を聞きながら100講を読むことによって少しずつ理解できるようになってきました。また、受験対策のポイントだけでなく将来実務を行っていく上でも非常に役に立つものばかりであると感じました。
私の受験生活は、仕事を行いながらの勉強であったため、時間の使い方は大切にしました。教材が概ね週末に届いたこともあり、ある程度時間が確保できた週末にDVDの視聴や100講の読み込みを行って、平日は土地と建物の書式を1問ずつ解答し、仕事が遅くなったときは無理をせず休養をとるようにしました。ただ、それだけでは時間が足りず、ICレコーダーにDVDの音声を録音して、通勤時や仕事の移動時間中もとにかく聴くようにしました。音声のみで聴いているためわからない箇所や曖昧に覚えている箇所などは何回も巻き戻して聞くことによって理論を定着させるようにしていきました。ようやく登記法や関連法についてわかるようになってきた頃に答練が始まりましたが、択一は設問の意味がわからず、書式はその影響で時間内に解答することができず、理解どころか平均点すら取ることもできませんでした。
択一では、法律独特の言い回しに慣れるのに苦労しました。それは、今まで条文をほとんど引かなかったためだと思い、復習には解答に書かれている条文を確認し関連付ける作業を行っていきました。書式では、基本パターンをしっかり覚えていないため、記入もれが多く登記原因など同じ箇所ばかり間違えていたので、復習には時間をかけて丁寧に行っていきました。
そして、過去問や答練の問題も時間内に解答できるようになり、1回目とは違う手ごたえをもって2回目の本試験を迎えましたが、前日から眠れないくらい緊張してしまい、当日も隣の人の消しゴムの消す振動や問題の余白を破る音なども聞こえて集中力が持続せず、択一は辛うじて足きりは免れましたが、書式が1点及ばず足きりにあって不合格になりました。
3回目の挑戦
受験勉強を始めてから3年目に入り、条文の言い回しにも慣れてきましたが、今まで何が足らなかったかを整理することから始めました。
択一に関しては、過去2回全滅で苦手にしていた民法の学習時間を大幅に増やし、条文の読み込みや問題を多く解きました。ただ、民法は条文も多く出題範囲も広いので、総則、物権、担保物権、相続のみにしておき、苦手意識をなくすようにしました。
書式に関しては、時間短縮を図るため、今まで取り組まなかった複素数による計算を、取扱説明書などを見ながら使えるようにしました。さらに、問題文で与えられた条件だけで電卓を叩かず作図のみを行い、問われている内容の理解と作図方法をしっかり身につける練習を繰り返しました。これは、自分の中に座標計算を行ってから作図を行うという悪しき理想があり、特に2回目の本試験で作図ができず失敗したので、図面を正確に書き上げてから座標計算を行うように変えていきました。この練習を繰り返し行うことで作図中に計算方法がひらめいたこともあり、また、図面が出来上がっているので申請書や座標計算に使う時間を増やすことができるようになっていきました。
択一も書式も苦手としていた分野を集中的に行うことで解答が速くなり、自信を持って3回目の本試験を迎えました。直前時期には自分のしてきたことをそのまま出せるようにあまり深入りせず、条文の確認や書式の基本パターンの確認のみにしました。また、体調管理を含めリラックスするようにしてきたかいもあって、試験が始まってからも自分のペースで解答することができましたが、座標が1点算出できず土地の書式は自信のもてる解答ではありませんでした。
筆記試験合格発表の日は、仕事で遠方まで出かけていたため、たまたま家にいた妻に受験番号を伝えて連絡を待っていました。そして、午後4時過ぎに電話が鳴り妻はこう言いました。「番号あったよ。おめでとう!」と。嬉しさのあまり言葉が出ず、実感がわかなかったので仕事をすぐに片付けて事務所に戻り、再度確認して自分の番号を見つけたときに合格したんだと実感がわいてきました。口述試験にあたり、対策資料を送付していただきましたが、本番の雰囲気を体験したいこともあり、模擬試験を本校で受けさせていただきました。今まで、DVDでしかお目にかかれなかった深田先生、松元先生を目の前にし、大変緊張したのは言うまでもありませんが、どのようなものかという事を経験したおかげで当日は緊張することなく落ち着いて回答することができました。
最後に
早稲田法科の通信教育を受講してからは送られてきた教材以外は使用しませんでした。それだけで本試験を突破できる内容がぎっしり詰まっていますし、わからない箇所は質問券で補えるのでこれで十分です。あとは、自分がどうしたいかでいい結果が必ず出るものと信じています。そして、受験に専念できる環境を作ってくれた妻に感謝します。
最後になりましたが、深田先生,松元先生をはじめ、答練の作問をしていただいた諸先生方、口述模擬試験の時に案内していただいた事務局の方々に大変感謝しています。本当にありがとうございました。