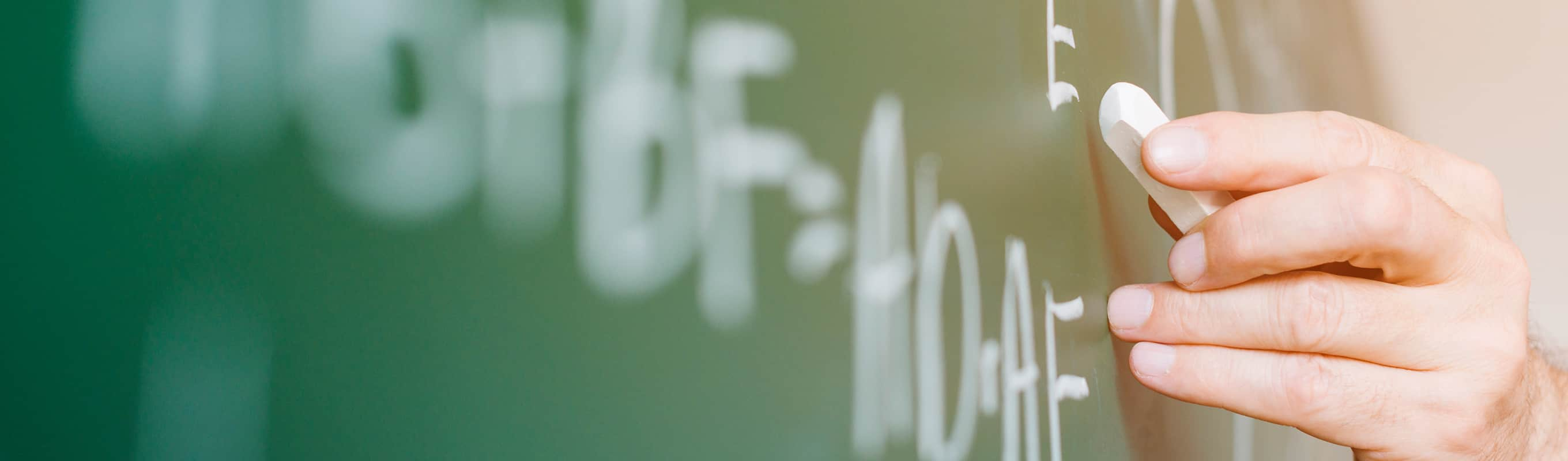私が早稲田法科を選んだ訳
子供が小さく(当時2歳と1歳)通学は無理だったので、はじめから通信講座を探していました。平成17年は不動産登記法改正のため、どの学校の通信講座も中断していましたが、一番早く開講していたのが早稲田法科でした。また一番価格が安かったのも大きな理由です。書店で手にとった「受験100講」も最初は全く内容はわからなかったものの、厚いけれどB5判の大きさが持ち運びやすそうだったのも理由のひとつです。
勉強をすすめていく上でパートナーとなるべき予備校選びは重要です。早稲田法科は、とても親身になってサポートしてくださいました。一年間の勉強で合格できたのは予備校選びを間違っていなかったからだと思っています。
私のバックグラウンド
第二子出産を機に退職したものの、何か仕事をしたくて、夫が薦めてくれたのが土地家屋調査士でした。ちなみに夫も私も全くの畑違いで最初は土地家屋調査士の仕事は何なのかも知らない状態でした。前年の17年に測量士補の試験を受け(これも通信で勉強)、その年の8月から調査士の講座を受講しました。測量士補のときも???でしたが、調査士の勉強はさらに輪をかけて???でした。何しろ読めない漢字が多かったですから。学生時代も文系でしたが、法律のことなど学んだことは一切ありませんでした。ただ、数学は好きで得意なほうでした。
受講講座と使用教材
終わってみれば、受講したのは「入門総合ビデオコース」と「全国答案練習DVDコース」だけです。勉強を始める前に書式練習講座もいくつか考えていたのですが、早稲田法科のスタッフの方に「初学者はまずは入門総合ビデオコースからです」といわれ、実際それだけで手一杯で書式練習講座までいきませんでした。全国答練はDVDをつけるかどうかで金額がかなり違うので迷いましたが、初学者の方は絶対に解説ビデオをつけたほうがいいと思います。講義中の講師の方々のお話の中に試験での重要な情報(「これはできなきゃいけない問題ですよ」「これは過去にも類似問題がでてますよ」「今年はこれがでますよ」など)がたくさんもりこまれているからです。それに、あまりのできなさに、講義中の講師の方々のフォロー(「まだできなくてもいいです。本番できればいいんです」など)がなかったらきっと12回全部やりとおせなかったでしょう。
使用教材は入門総合ビデオコースについていた「100講(1)理論編」「100講(3)書式編」です。過去の合格体験談に全国答練が始まる前に過去問を一通りやったほうがいいとあり、「調査士本試験問題と詳細解説」という過去問をやりました。
私が失敗したのは、民法等周辺法への対応です。入門総合ビデオコースのテキストを用いていたのですが、それだけでは不十分でした。全国答練に入ってそれに気づき、あわてて「100講(2)理論編」を購入しました。「六法」も軽視していたつけが全国答練であらわれました。それまで六法をほとんど開いたことがなく、その習慣もついていませんでした。入門総合ビデオコースのときから条文をチェックすべきだと思います(解説書に出題に関連する条文番号がかかれているので、その条文を読んでチェック印をするだけでいいのです。するといろんな問題を解くうちにポイントとなる条文がわかってきます。また法律の独特の言い回しにも慣れてきます。)
時間の使い方
過去の合格体験談を読むと、一回で合格されているのは皆さん会社を退職して時間がある程度確保できる方ばかりでした。私の場合、子供が小さく、昼間は全く時間がとれません。お勤めに出ている方なら通勤途中でテキストを読めたりするのでしょうが、それもできません。下手に昼間勉強しようとすると、子供が邪魔になってイライラするだけなので、昼間は勉強しない!と決め、子供を寝かしつけてから集中してやりました。それでも夜中子供が泣いて起きて中断されることもしばしばでした。「ママ、勉強しないで~」と泣かれたことも多々ありました。まだ私が横にずっといないと不安になるようで、結局机を寝室に持ち込み、子供といっしょに9時に就寝し、私だけ3時に起きて7時すぎまで勉強しました(朝方は子供が起きることが少なかったので)人それぞれ状況は違うでしょうが、だれでも一日は24時間で平等です。人をうらやんでもしようがないので、与えられた状況の中でやりくりするしかないのでしょうね。私の場合、あまりに子供や主人に負担を強いて申し訳ないという気持ちが強かったので、絶対一発合格しなきゃと切羽詰って勉強していたように思います。
早稲田法科の有効な活用方法
早稲田法科のパンフレットに「早稲田法科なら一年で合格うかる」というコピーが載っていました。さらにいうなら「早稲田法科なら通信でも一年で合格うかる」と付け加えたいと思います。ただ、そのためには、通信教材と一緒に送られてくる学習のしおりや学習計画表のとおりに学習をすすめることが必要です。たとえば100講の通読、熟読、再読などは書いてしまうと簡単そうですが実際やろうとするとかなり厳しいものがあります。でも信じてコツコツそのとおりに勉強すれば必ず合格レベルまで到達できます。通信の場合、質問票が10枚までに限られていますが、逆に限られている分、大事に使おうと思いますから、なるべく自分で理解するよう頭を使うようになります。私の場合、質問票というより相談票で「今、このような勉強をしているが、これでいいか」だとか「試験まで2ヶ月をきったが、効果的な学習方法は?」「試験当日の心構えを教えてください」などなど最後はお悩み相談でした。それでも親身になってご回答いただき、ずいぶん励まされました。前述のように電卓の使い方を質問したときには松元先生ご自身から直接お電話をいただき、いたく感動しました。こんな学校はほかにないのではないでしょうか。
どうぞ自分と早稲田法科を信じてがんばってください。みごと栄冠を手にしてください。